・「コミック・ワイドショー」 Vol.0(2004、洋泉社)
【雑誌】・「マンガ ムー」̺1(2004、学研)
【雑誌】・「マンガ ムー」̺2(2004、学研)
・「UFO極秘ファイル」 矢追純一(2004、竹書房)
・「UFO機密ファイル」 矢追純一(2004、竹書房)
【雑誌】・「週刊少年ジャンプ」46号(2004、集英社)
【雑誌】・「週刊少年ジャンプ」47号(2004、集英社)
【雑誌】・「週刊少年ジャンプ」48号(2004、集英社)
【雑誌】・「コミックまぁるまん」11月号(2004、ぶんか社)
【雑誌】・「コミックまぁるまん」12月号(2004、ぶんか社)
・「パチスロ7Jr.」 11月号(2004、蒼竜社)
【CD】・ロボキッスをよりロボソング風に替え歌してみました
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2004、テレビ東京)
【CD】・「ロボキッス」 W(ダブルユー)(2004、zetima)(以下、ロボット娘ソングを適当に羅列していきます)
【CD】・「ROBOT」 榊原郁恵(1980、日本コロムビア)
【CD】・「パンチの嵐」 ハニーパンチ(1999)
【PV】・「ラッキーチャチャチャ!」 ミニモニ。(2004、zetima)
【レコード】・「バーバラ・セクサロイド」 ヤプーズ(1987、テイチク)
【CD】・「UFO」 電気グルーヴ(1991、Sony Records Trefort)
・「鬼刃流転 孤高の天才剣士柳左近」 山上たつひこ(1990、マガジンハウス)
【小説】・「駿河城御前試合」 南條範夫(1993、徳間書店)
・「シグルイ」(1)〜(2) 南條範夫、山口貴由(2004、秋田書店)
【映画】・「DEVILMAN デビルマン」感想追記
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2004、テレビ東京)
・「コミック・ワイドショー」 Vol.0(2004、洋泉社) [amazon]
一見、コアマガジンの本かと思ったら洋泉社だった。要するに、テレビのワイドショーネタのマンガで1冊つくったのである。
青林堂や青林工藝舎系の作家が多くて、作品のツブが揃っている。
まずはワイドショーに登場しそうなタレント、スポーツ選手などで「愛」という名前の人々が殺し合う駕籠真太郎「バトル・ロ愛ヤル」が面白い。主役が福原愛で、しかもにくったらしく描かれているところなんか、おおいに共感できる。
かわかずお「ビビルマン」は、映画「デビルマン」のひどさを原作風の絵柄でやっちまおうという企画で、内容自体は面白い。その子供っぽく、ガキ大将的な態度は大きく買うものの、ペキンバー田野辺とギンティ小林の最後の解説は映画へのマジな批判になってしまっていて「ワイドショー」という下世話な観点からはややはずれてしまっていると思う。
根本敬はおそらく大得意ネタで風格すら漂うが、私が衝撃を受けたのはまず大久保ニュー「From Girl's Room」。フツーのOLが主人公。彼女には、あきらかにさとう珠緒がモデルの先輩OLがいる。もちろん同性には嫌われまくり。しかし、その「さとう先輩」を嫌っているグループにも違和感を感じる主人公は、その「反さとう先輩グループ」に嫌気がさしてとうとうひと言申してしまう……という内容。
「さとう先輩」のあり方を完全否定しない姿勢に深く感動した。知性って、こういうもんだ(誉めすぎか)。
もうひとつは服部元信「ワイドショー無間地獄」。ワイドショー好きな、徹底して下世話なおばはんが、上から落ちてきたクボヅカに激突、クボヅカとともにワイドショーネタの怨念のタマリ「ワイドショー無間地獄」に落ちてしまう。果たして帰れるのか……という内容。
「徹底して下世話なアイテムだけで、人間に救済はあるのか!?」にせまった内容ですらあると思う(これも誉めすぎか)。
(04.1029)
【雑誌】・「マンガ ムー」̺1(2004、学研)
「ムーがマンガになった!」というワケで、ムーに載るような記事をマンガにして集めた雑誌。
そうだなあ……こういうことにものすごく詳しくてツッコミを入れられる人か、「ムー」の斬り口そのものが好きな人でないと読むのが辛いかも……。
あすかあきおが例のキャラクターで新作「ネオ・パラダイムASUKA 火星の巨大生物 サンドワーム」を。まあいつもどおりですけど……80年代のコロコロノリがちょっと楽しいかなっていうくらいで。
バンチで賞金ウン千万円とった木ノ花さくやは「『スカイフィッシュ』襲撃事件を追う!」というのを描いてます。
あと、なぜかタイム涼介が1ページ描いていた。
(04.1029)
【雑誌】・「マンガ ムー」̺2(2004、学研)
公式ページ。
この雑誌、けっきょく新宿紀伊国屋の独立したコミックのコーナーで見つけたんだけど、厳密には雑誌というより別冊というかムック的扱いなので、どこに置いてあるかわからないんですよね。
別にねえ、そんなに私は以前からムーっ子ってわけでもないんで、「ムーありますか? ムーありますか?」って書店員に所在を聞くという行為がなんだかとても恥ずかしく、しまいに言いようのない怒りになっていきました。
内容ですが、まあ前号とそう変わらんです。MMRもそうですが、こういうタイプのモノにいまいちなじめないのは、探求者が謎を探求しても、彼自身も、世界も、何も変わらないからなんです。まあ「記事」としてはそれでいいのかもしれないけど、マンガという飛躍可能なメディアにおいてそれはどうよというのが、私の偽らざる気持ちです。
さらに突っ込んだ内容ならまだいいけど、ぜったい反証を都合良く隠していると思うし……。今号の木ノ花さくや「『体外離脱』の謎を探る」とか、その典型なんですよねえ……まあ木ノ花さくやのマンガはこういう説明的なプロットをうまく消化しているとは思うんですが。
後は、フォトン・ベルト、「ヒロシマ原爆はナチス製だった!!」、つのだじろうの不思議体験マンガ、秋山眞人の前世シミュレーション、あすかあきお「ネオ・パラダイムASUKA 火星の第2人面岩とアルテミュア文明の謎」とかが載ってます。
個人的には、もっとムチャクチャな話が載っていた方がいいと思いますねェ。
また、なぜかタイム涼介が1ページ描いていた。
(04.1029)
・「UFO極秘ファイル」 矢追純一(2004、竹書房) [amazon]
矢追純一の著作をベースにしたマンガを複数のマンガ家が描いている、コンビニペーパーバック本。
amazonの感想を読むと、宇宙開発やUFOに詳しいとかなりトンデモ本的に笑える内容らしいが、哀しいかな知識不足でよくわかりませんでした。
どうも、私は矢追純一はもともとあまり楽しめなくて、理由はねえ、あまりにもテキトーすぎるから。最初から信じられないから、「だまされる興奮」もないんですよ。
マンガとしては、どうしても内容が内容だけに説明的になりがちな作品が多かったと思います。
実は「ケネス・アーノルドが軍のパイロットとして描かれている」、「1947年当時の話なのにヘリコプターの『アパッチ』が出てくる」という指摘につられてネット通販で古書として買ったんですが、読んでみたらそこんところの描写は前田俊夫じゃないですか。
そりゃ大いなる間違いかもしれないが、こうした「矢追氏」という顔が全面に出ている企画で唯一記憶に残るのはやっぱり前田俊夫なんだよなあ。グレイでない宇宙人や、ぜんぜん資料を見てなさそうな宇宙船を描いているのも彼でした(「ロズウェル事件」のUFOに、わざとなんだろうけどイマ風のデザインをした木ノ花さくやの気の遣いようとは正反対)。
それと、四国の中学生が小さい小さいUFOをつかまえて中に水を入れたりかなり乱暴なことをしたら消えちゃった「介良事件」がマンガ化されているのは良かった。いや、この事件、なんだか好きなんですよ。
(04.1029)
・「UFO機密ファイル」 矢追純一(2004、竹書房) [amazon]
矢追純一の著作をベースにしたマンガを複数のマンガ家が描いている、コンビニペーパーバック本第2弾。
前田俊夫御大がラインナップされていない時点でかなり興味をそがれるが、吠夢「人々に夜空を見上げさせた男・矢追純一物語」は、わりと良かった。
矢追氏が「UFOはあくまでも『釣り』であって、本当はもっと人々に視野を広く持ってもらいたい」というあまりにも胡散臭い動機で「11PM」のUFO特番を始めたことなどが描いてあります。
それと、本書全体において矢追氏自身のコメントがマンガ作品の間に頻繁に入るのですが、
「矢追 そうそう。だからじつは宇宙人やUFOのことを考えるのは無意味かもしれないんですよ。」(p254)
……というコメントには笑ってしまった。無意味なことを熟考した果てに一回転してしまった発言というか……。まあでも公平に見るならば、後に続く文を読んでみても矢追氏の無意識化には「UFO、宇宙人=神、絶対者」というイメージがあるのではないかとは思ったよ。それがいいか悪いかは別にして。
(04.1029)
【雑誌】・「週刊少年ジャンプ」46号(2004、集英社)
51ページの読みきり作品、草薙勉「セイテン大帝」。バカだが元気な少年・島原とらみを探しに転校してきた美少女。実は、この少女は三蔵法師の生まれ変わりで、「獣人」とともに妖怪退治の使命を負っている。とらみは孫悟空の生まれ変わりらしいが、説明してもちっともわかってくれない。
だが、とらみが励ましてやっていた病弱な少女に怪物が乗り移って……。
暴れん坊だが弱者には優しい少年、少年にふりまわされるツッコミ役の少女、病弱で、みんなの知らない少年の良さを知っている少女と短いページ数の中で描き分けができている。とらみの獣人への変身シーンはもうちょっとコマを使ってもよかったが、ひさしぶりに掛け値なしに「元気なマンガ」が読めて嬉しかったです。
コマ運びも見やすい。
和月伸宏「武装錬金」。やられキャラだと思っていた少年のチャクラムの武装錬金が超カッコエエー! 敵、味方、両者の凄さを見せつけつつ、なおかつ敵優勢は変わらないというこの描写。もう天下一品だ。
(04.1029)
【雑誌】・「週刊少年ジャンプ」47号(2004、集英社)
荒木飛呂彦「スティール・ボール・ラン」は、連載が再開したと思ったら先週と合わせての前後編だったのね。後編の展開は面白かったけど、足の吹っ飛んだジャイロはケガの手当をしないのかとか、スタンド能力のない人間にもスタンドは見えるのかとか、細かいところが気になった。
ジョースターの「爪が回る」っていうのは何かの前兆かと思ったら、本当に爪が回るだけの能力だったのには驚いたけどね。
45ページの読みきり、久世蘭「湖賊」。16世紀の琵琶湖を舞台に、海賊ではなく「湖賊」(正確には関所の番人か?)のにいちゃんが活躍する時代アクション。着想は面白いが、ネームが少々多く、コマ運びが見にくい気がした。また、根本的に「関所」というのは各地域の治安維持という利点と、流通をさまたげるという欠点両方あったわけで、そこら辺まで踏み込んで描くと面白いのにな、と思いましたよ。
(04.1029)
【雑誌】・「週刊少年ジャンプ」48号(2004、集英社)
ここのところの読みきり作品はなかなかのものが多い。
吉川雅之「マッストレート」は、あるボディビルダーの筋肉に憧れて筋肉バカになった主人公が、かつての憧れのビルダーが「見せかけの筋肉」とボクサーにバカにされたことに腹を立て、リングに上がる……という話。
伝統派空手同様、格闘技マンガではボディビルは「役に立たない」、「見せかけだけ」と言われてきた。その常識を覆すというか、「元気を与える」という点ではビルダーの存在意義は何ら他の格闘技と変わるものではない、とするテーマは面白い。 「餓狼伝」における伝統派空手の扱いに似ているというか。
もし、「あらかじめ筋肉のついた者がボクシングをやると何が有利で、何が不利か」を細かく描ければ、連載になっても面白いかなと思った。
特別読切KAITO「ハピマジ」は、マジックでだれでも煙に巻いてしまう少年を主人公にしたギャグマンガ。こういうのは種明かしナシだとちょっと苦しいかな?
でも基本的にマジックを題材にしたマンガはむずかしい気はします。
(04.1029)
【雑誌】・「コミックまぁるまん」11月号(2004、ぶんか社)
グラビア&成年マンガ誌。巻頭グラビアは小倉優子。
矢野健太郎「アキれちゃダメですゥ」は第10話「エロエロRQはいかがですゥの巻」。アキがレースクイーンのコスプレで、アキバでエロゲーのチラシ配り。そのゲームが「RQ陵辱調教&純愛泣きゲーチーム運営シミュレーション」ってのが(笑)。
徳光康之「握手戦記 握手ボンバー」は第9回「決戦!! 撮影スタジオランチタイム」。吉木りさという子の水着撮影現場を取材、握手しようというレポマンガ。それにしても作者はまったくといっていいほど戦隊モノを知らないというのは本当なのか?
他にマンガは白虎丸、尾山泰永ほか。ちょこっと坂本しゅうじが描いていて懐かしかった。
(04.1029)
【雑誌】・「コミックまぁるまん」12月号(2004、ぶんか社)
グラビア&成年マンガ誌。巻頭グラビアは川村ゆきえ。今月21日発売だから、探せばまだ売ってるかな……?
矢野健太郎「アキれちゃダメですゥ」が載ってない! 代わりなのか何なのか、あろひろし「お隣のくされ縁ジェル」というのが載ってた。「フィギュアづくりの参考にしたいから」と幼なじみに身体をさわられまくるアイドルの女の子の話。少し女の子の顔をイマドキ風にしてますね。
以前、コミックボンボンで「プラレス三四郎」の神矢みのるが、絵柄をムリヤリイマドキアニメ絵風にしていてすごく哀しかった記憶がありますが、こういうのはホント、むずかしいもんです。
もうひとつ読みきりが、久寿川なるお「バスマニアガイド」。バスマニアのバスガイドと、バスマニアのにいちゃんがいろいろと……という話。この人の絵はけっこう好き。イマドキのエロゲーっぽい感じがないから。見ていて落ち着く。
徳光康之「握手戦記 握手ボンバー」は第10回「ポラ……知りそめし頃に……」。レースクイーン撮影会に行った話。
マンガは他に、白虎丸、灰嶋克茶など。
(04.1029)
・「パチスロ7Jr.」 11月号(2004、蒼竜社)
人は何かを手に入れる度に何かを捨てている……でも
堀田は違う たった一人で戦っている……
俺たちが捨てちまったものを
必死で守ろうと−−
感想が遅れて申し訳ない。今月号は雑誌自体の表紙も「ヤマアラシ」ですね。
宮塚タケシ、原作/鶴岡法斎「ヤマアラシ」は、主人公・堀田とスロをやめてサラリーマンになり、現在は妻子もある福田とのエピソード。福田からスロットを教わっていた過去。あれから年月が経ち、かたや今はスロプロの堀田、カタギの福田。
「カタギになった者が、世間的にはフラついている者に悪気もなく説教めいたことを言うが、言われた方はものすごく腹が立つ」っていう状況は、……まぁ立場は違うけどスッゴイよくわかる。
さらに本作がイイと思うのは、お話は1話完結で毎回わかりやすいんだけど、堀田自身は自分の悩みに容易に着地点を見つけようとしない。
私は、この物語の結末がスロットマンガである以上「これからも打ち続けるしかない」という結末でも、あるいはもっと逸脱して意外な居場所を堀田が見つけても、どっちでもいいとは思ってます。
私の書く感想は、本当に印象だけで書くことのきわみ。で、その曖昧な印象だけで書くと、青春のイライラみたいなものを書く作品はマンガでもいくつもあるけど、着地点を見つけないままの彷徨を描き、そしてどこかに「誇り」を忘れてないのって最近ではこの作品くらいしか思い浮かばないんですよね。
普通のマンガって、とにかく主人公を居場所に着地させることが物語の進行の原動力になっている場合が最近多いから。
それを考えると「ヤマアラシ」は、アニメの(マンガは読んだことないんで)「カムイ外伝」とか、そういう「放浪もの」に近いかもしれないですね。実際に旅に出たこともあったし。
(04.1027)
【CD】・ロボキッスをよりロボソング風に替え歌してみました [amazon]
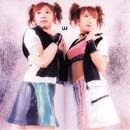
W(ダブルユー)の曲「ロボキッス」に関しては、【CD】・「ロボキッス」 W(ダブルユー)(2004、zetima)(以下、ロボット娘ソングを適当に羅列していきます)に感想を書いたんですが、歌詞があまりにもロボソングらしくないので、勝手に変えてみました。
すごい あのこは ロビンちゃん
やばい あいつは ウォーズマン
誰も彼もが ヒューマノイド?
ダメダメ
何使ってんの ポケコン
デートのプレゼント ファミコン
嗜好重なる ロリコン
などなど
合体も
できてて当然
好き好きっす キスをください
好き好きっす 挑発無限大
好き好きっす 心は変わるわ
好き好きっす ロボットだっても
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
ロボガキ
これで あの子と 戦闘
それで 彼氏が フェード・イン
ジムが弱いよ 連邦
ダメダメ
計算じゃなく 哀しい!
なぜか両目から 冷却水
空山基の絵は ありがたく
いただけ
プログラム 「心」を学習
好き好きっす キスをください
好き好きっす 薬はポーションね
好き好きっす 「萌え」はわかるわ
好き好きっす ロボットだっても
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
ロボデキ
(調子ン乗って本当はないけど三番)
すごい あのこは ウランちゃん
やばい あいつは 28号
手先が不器用 コバルト?
ダメダメ
何買ってんの AIBO
トコトコ 歩く ASIMO
スカート 長い テムザック
などなど
三原則
わかって当然
好き好きっす キスをください
好き好きっす スキス スキスキスー
好き好きっす 人間なら友達だけど
好き好きっす ロボットだからロボダッチ
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
シャバラ ラン ラン ラン ラン ラーラ
ロボガリ
(04.1027)
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2004、テレビ東京)
10月24日放送分。
公式ページ。
おんがくの時間2004。
要するに音楽を聴いてジェスチャーをして当てるとか、特定の方法(身体を叩く、ドラムを叩く、波の音を出す小豆を使う)で曲を演奏(?)して当てるとか、そういうゲーム。
内容について書く前に書きますが、このハロモニ。の感想を読んでいる人というのはどういう層なんでしょうか。娘。が好きでハロモニ。を見ている人はわかりますが、それ以外の人で読んでいる人はいるのでしょうか。
自分では、「興味のない人にも何とか読んでもらおう」と工夫しているつもりなんです。というわけで、今日はだれも知りたくない私の日常生活から話を始めましょう。
まず、午後9時から他人の誹謗中傷を受けるという仕事をします。これはむろん抽象的な意味でです。クレーム処理係とかそんなんじゃありません。
そして昼。「いいとも」を見ながら昼食をとります。「いいとも」に出てくるシロウトは、仕込みの人がかなり含まれていることを知っていますか!! まあそんなことはどうでもいいですね。(♪どうでもいーですよー)(だいたひかるの声で)
そして午後1時。「小堺一機の髪の色はヘンだ、世界一ヘンだ」とつぶやきながら仕事再開。道行く主婦たちの蔑んだクスクス笑いが聞こえてきますが、無視します。
その後、「穴を掘って埋める」、「面白そうな話だと思ってよくよく聞いたら、すごく不愉快な話だった」、「面白そうな話だと思って聞いたら、自慢話だった」、などの過程を経て、「あー正面の酒屋の息子ブン殴ってやりてえ」などと思いながら、一日が終わります。
職場の特徴としては、異常に女っ気がありません。ムショ暮らしみたいなモンです。
支給された週刊誌の表4のダイエットの広告の「使用後」の女の人の写真をを見てコーフンするくらいしか道がありません。
そんな光景を、道行く主婦(柴田理恵そっくりで性格を一億倍悪くしたような人相)がバカにしたように見ています。そいつの連れているガキは、キャベツ畑人形そっくりでちっともかわいくありません。しかも首のとれたキューピー人形をいつも持っています。
家に帰ってくると、「バーカバーカ」という内容の留守電が5件。呼び鈴がなったので玄関に出てみると、小学校低学年の子供を二人連れ、菓子折を持って同情をひこうとする新聞勧誘員が立っている。
部屋の窓から見える家の前で、木村太郎そっくりのオッサンがさるまたいっちょうで植木に水をやっている姿が異常にウザい。
まあ、そんなこんなで楽しみが本当の本当に「ハロモニ。」しかありません。
かわいそうでしょ? 同情してください! なんか差し入れしてください!
あと、こういうことを書くと「どうしちゃったんですかー、新田さん」とか言ってくる人がいますが、どうもこうもねェよ!
元からこういうことを書きたいんだけど、おさえてるんだよ。
そんなことを言うキミは、これから拉致監禁して首のとれたキューピー人形を持った木村太郎ソックリのおっさんのビデオを5年間見せ続けます。
それにしても本当に木村太郎はムカつきますね。安藤優子はそんな太郎をなぜ許しているのだろうか。
さて(してやったりという顔であたりを見回しながら)、メンバーのファッションも秋らしくなってきました。とくに六期は全員似たようなミニスカートで揃えてました。まあ違うのかもしれないけど、オッサンの私には似たように見えました。
ネタばらしをしそうになった小川は、「ゴロッキーズ」でネタばらしをしてしまったことを知っていると余計に面白い。
モーヲタのガキさん、シャ乱Qヲタならず、という失態を。しかし他の二人(亀井&道重)は疑問を抱かなかったのだろうか?
「クイズの答えがわからない」&「どーせ私はボケることもできないんだよなー」と始終困り顔の高橋愛が、私の嗜虐心を満足させました。
「ズンドコ節」を知らないと答えた飯田さんは、ハロモニ。のオンエアを見てないということが発覚。矢口さんが「ミラクル!」と叫んでましたが、ミラクルというよりはコレは普通にマズい事態なのでは(「公園通り三丁目」で、ときどき亀井が氷川きよしみたいなキャラを演じ、ズンドコ節も歌っていた……はず。忘れた)。
小川がネタをばらしそうになったことを指摘されている後ろで腕を組んで、すごい冷たい目でその光景を見ている藤本美貴ティーに注目してみてください。なかなかゾクッとします。
公園通り三丁目。保田さんのオヤジキャラは、もうやめた方がいいと思います。別に面白くないし……。
今回も、ガキさんは髪型はいつもどおりの女の子なのにヒゲだけ付けていた。
「アターレ飯田」が出てきたので、私は個人的に満足です。
細木数子ネタは、ぜんぶ飛ばしました。わーたーしーはー、かわいい女の子が見たいのー。何でわざわざ気持ち悪い姿になったのを見ないといけないのよ。まあだいたい細木数子に21世紀のテレビ界が頼っているというのがちょっと信じられない。
HPH。ゲストは「渡良瀬橋」を出す松浦亜弥。高飛車キャラで登場、ということでおじゃマルシェ紺野(今回はキャメイは休み)のテンションが下がる、というのをやっていましたが、私は紺野が(余裕がないだけに)内心ムカついていると解釈。
実は、HPHだけを見て、私は「紺野はあややに苦手意識を感じている」説を勝手に唱えています。
スタジオライブは、あやや。
あと、ガラクタで演奏するバンドがゲストに出てた。あの上戸はどうやって音程を変えられるの? 見ててよくわかりませんでした。
アップトゥボーイ、売ってないから死のう。
昔の「アクトレス」のラジオのCMが気持ち悪い(アニメ「ドカベン」の声をやってた人がオドオドした少年の声を担当)から、死のう。
それではみなさん、夢をあきらめないで、自分を信じて生きていってください。
・前回の放送
(04.1025)
【CD】・「ロボキッス」 W(ダブルユー)(2004、zetima)(以下、ロボット娘ソングを適当に羅列していきます) [amazon]
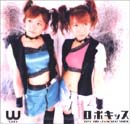
作詞・作曲:つんく、編曲:高橋諭一。「ゴロッキーズ」という番組で「どれだけ目を開けたままにしていられるか」という実に他愛ないゲームをしていたとき、おそらくスタジオのライトの強さからだろうが藤本美貴が両目から涙をポロポロこぼしていた。
そんときに、「天の声」のキー坊が「初めて涙を流したアンドロイドみたい」というようなことを言ったような言わなかったような(この辺曖昧)。
とにかくまあ、「ロボット(アンドロイド)が涙を流す」というシチュエーションは実によく使われるんです。ロボット=感情がない、だけどそれを揺り動かすものがあるんだよ、というね。
考えてみると、影の大物みたいなのに主人公が楯突いて殺されそうになったとき、その大物が「おまえのようなやつはひさしぶりじゃ」とか言って助けてくれたりするのと近いよね。まあ何が近いかはみんなへの宿題だ(便利な書き方)。
さて、顔も背格好も揃っていてダンスもできるW(ダブルユー)の二人がロボットの歌を歌うのは歴史の必然とさえいえるのだが、「ロボキッス」というタイトルを聞いたときにそれが完璧に遂行されるかどうかが不安だった。
とにかく最近のハロプロ仕事は不安が多すぎるし、その欠落を脳内補完したりこうしたテキスト上でレトリックで埋めるほど私はヒマではない(「うたばん」での、後浦なつみへの石橋&中居のつっこみはそのまま視聴者の意見と考えるべき)。
結果は、まあ音楽的なことはわからないんだけど「歌詞はちっともロボットっぽくない(むしろ適当)のに、曲とアレンジとダンスでみごとにロボットっぽく見せている」という、珍しいと言えば珍しい曲となった。
まず、つんくにロボットがらみの歌詞を書かせてうまくできるとは思っていなかった。この人は「男の子の妄想する理想の女の子の心理・行動」を、旧来の……たとえば「デュオU&U」からなら「好きよキャプテン」(松本隆)のような少女マンガチックなものを実にうまい具合に現代風にアレンジするか、あるいはまったくの意味不明な歌詞が得意。「あなたにとって、私は○○」みたいな比喩的な歌詞は得意じゃないから。
というわけで、「♪ロボロボ」といかにも付け焼き刃なフレーズが入ったり、「好き好きっす キスはわかるわ 好き好きっす ロボットだっても」と言いつつ「いつまでも子供じゃないのね」とまったくもって矛盾する歌詞になっていたりと(ロボットも成長するのかよ! おい!)、いつもどおりのメチャクチャ歌詞ぶりではある。
だが、つんくの無意味歌詞はさらにひどいと「GET UP! ラッパー」[amazon]みたいにほんっっとうにわけのわからないところまで解体してしまうので、今回はOK。まあ阿久悠だったら許さないでしょうけどね。
今回はむしろ、振り付けとのトータル的な曲である要素が非常に強い。とくに、曲の出だしの、加護の背中のネジを巻いた辻がめまいを起こし、あわてた加護が自転車の空気入れみたいな仕草で空気を入れると瞬時に辻が復活してから曲がドンッ、と始まるタイミングがものすごくカッコいい。この出だしの数秒だけで、「ロボット」を表現してる。だから歌詞がそんなにロボットと関係なくても許される。
そしてさんざん激しいダンスをやっておきながら、オルゴールの人形の動きが止まるようなイメージで静かに動きを止める二人。この振り付けは本当に傑作。だれがやってるんだろ?
こうして見事にロボットデビューを果たしたダブルユーに対し、スタンディングオベーションしたい私だったが、世間はどう思ってるんですかね。いまだに「どっちがどっちかわかんな〜い」とか「加護ちゃん太ったな〜」とか言ってるだけなんでしょ。
そりゃ日本にカクメイなんか起きるわけないですよ。みんな細木和子とか「万引きGメン」のテレビとかだけ観てりゃいいんでしょどうせさー。
っつーことで、実に手持ちのコマが少ないながら「ロボット女の子もの」の曲を以下に紹介したいですよ。なんかAbout Japan [テクノポップ] の企画みたいだけど、当然あっちの方が千億倍くらいちゃんとしているので、テクノ関係で気になることがあったらそっちを観た方がいいです。
(以下に続く)
(04.1023)
【CD】・「ROBOT」 榊原郁恵(1980、日本コロムビア)
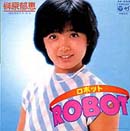
「郁恵自身-25th Anniversary edition」[amazon]や「ベスト・セレクション 榊原郁恵」[amazon]などに収録されているので、今でも聞けると思います。
作詞:松本 隆、作曲:筒美京平、編曲:船山基紀。1980年6月1日リリースだそうです。曲紹介の前に、まずジャケットのぞんざいさを観ていただきたい。ちっともロボットっぽくないばかりか、「夢みるマイ・ボーイ」(下部参照)という曲のジャケとほとんど変わんないじゃんかヨ! 昔のレコードってジャケ写が本当にテキトーなんだよなァ。
これはもう本当にロボット・ソングの傑作です。私が決めた。まあ松本隆にすりゃ、これくらいのレベルの歌詞は鼻ほじってても書けただろうしね。「月だけが夜の空を 彩り ため息のほうき星が 流れる」という微妙にSF&ファンタジックな歌詞に続き、「胸の歯車が錆びつく」、「胸のスイッチ押してね」といったロボットっぽい歌詞を散りばめる。
で、内容は「私は愛するあなたの言いなりよ」というのが、微妙に示唆されています。ロボットだから。要するに「恋の奴隷」みたいな歌詞を、テクノポップっぽい曲調と歌詞でコーティングしてある。
まあフェミニズムの人は難色を示すかもしれないがけっきょく、この「恋の奴隷+テクノロジー」っていう感性はいまでもアニメやゲームの「メイド型ロボット」なんかに引き継がれてるってコトですね。やっぱり日本にカクメイは起きないですね。
いや起きてるか。「おにいさま、私の『シモベ』になりなさい!」だもんね。ロボットじゃないけどね。

アレンジにもシンセとか使ってますし、衣装もロボットっぽかったんですよ。記憶を頼りに書いてますが、真四角の布を張り合わせたみたいな衣装で「ロボットっぽい真四角さ」を表していたと思う。
この曲の白眉は、そうしたテクノポップ的展開の後に「♪あな〜た〜が〜 好き〜なの〜」と急に人間に戻ったようなやわらかい振り付けになって榊原郁恵が歌うところ。当時、中学生だった私もあまりにベタな展開にちょっと笑ってしまったんだけど、最後までロボットだとこの当時のメジャーシーンでは納得されなかった、のかな。やっぱり人間的な部分が必要だったということで、そういう「オチ」みたいのが付いてます。
(以下に続く)
(04.1023)
【CD】・「パンチの嵐」 ハニーパンチ(1999)
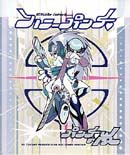
この「パンチの嵐」に入っていた「サイボーグ純情派」という曲が、私のお気に入りロボットソングです。
作詞:MIYA、作曲・編曲:DJ TAKAWO。
「♪存在の意義をさがして 今あなたにたどりついた 心がリズムを刻み出す 私サイボーグ」という出だしで始まる。「ハニーパンチ」ってのはクラブ中心に活動してた女の子二人ヴォーカルのユニットだったらしいんだけど、実物は見てません。
DJ TAKAWOは、確か「ビートマニア」の曲とかつくってる人じゃなかったかな。
「慎吾ママ」のコスプレで「おはスタ」に出たことがあるのが記憶に新しいですね(だれも知らない)。
「サイボーグ」ってことになってますが、歌詞を読むと完全に「ロボット」ですね。
歌詞全体がサイボーグの比喩になっていて、これはそうとうよくでてきます。
「ちょっぴりだけね 教えてあげる な・い・しょ・好きな人くらい守れる乙女」っつって、完全に「戦闘美少女」だねこりゃ。榊原郁恵の「ロボット」と比べるとポジティヴになっています。
インディーズなんだけど、とってもイイ曲なんでだれかにカバーしてほしいという妄想にかられる。ハロプロならダブルユー、高橋愛、メロン記念日あたりでどうでしょうか。どうでしょうかって言われてもね。わかってますよ。
ところで、同じCDに収録されている曲「いい事に気づいちゃった!!」も歌詞は衝撃でした。
「いい事に 気づいちゃった そこには何にもないってね いいことに 気づいたら 何から何までいい感じ」
って明るく歌う。こういう虚無感を越えて明るく生きていこう、という方向性はどことなく有頂天の「GUN」に通じるものがある。手に入りにくいかもしれませんが、オススメです。
(以下に続く)
(04.1023)
【PV】・「ラッキーチャチャチャ!」 ミニモニ。(2004、zetima) [amazon]

ミニモニ。のラストシングル、「ラッキーチャチャチャ!」については、発売当時ここに感想を書いたんですが、こっちはシングルVです。PVなのに、リリース前にはほとんど流れないという不思議なものです。
歌詞はロボットとまるで関係ありませんが、このシングルVのストーリーは桃のパフェみたいなやつの工場に忍び込んだミニモニ。の4人が、パフェ食べたさに機械を勝手に作動、工場内のロボット(4人が演じている)が暴走してメチャクチャになるというものです。
「ロボキッス」の振り付けに小悪魔的演出があるのに対し、このシングルVのロボットは完全にツナギを着た作業用です。
ま、もしかしてコレが「ロボキッス」のヒントになってるのかも、とかは少しだけ思います。
ミニモニ。のPVは、どれもよくできてます。
(以下に続く)
(04.1023)
【レコード】・「バーバラ・セクサロイド」 ヤプーズ(1987、テイチク)
作詞:戸川純 作曲:吉川洋一郎。CD「ヤプーズ計画」[amazon]などで聞けると思います。
実はキチンと聞いたことないんですよね。スイマセン。しかし、セクサロイドを87年の時点で歌詞にするなんて、やるなァと思いますよ。80年段階での郁恵ちゃんロボットが「恋のドレイ」ですからね。そこら辺を挑発してんですよね。
(以下に続く)
(04.1023)
【CD】・「UFO」 電気グルーヴ(1991、Sony Records Trefort) [amazon]
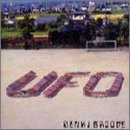
このアルバムの中の「メカニカル娘」。
作詞・作曲:石野卓球。やっぱり女の子の「属性」をメカとかエレクトロニクスとかにたとえるという王道的なやり方で、たとえも榊原郁恵の「ROBOT」みたいに一般視聴者には合わせてなくて、ほとんどぜんぶの表現を「みんなのうた」的にというか、童謡的にメカでたとえちゃってます。
この曲、確かライブで見たときは他の曲と同様、激しいアレンジでがなってたような記憶があるが、アルバム全体の緩急のためかささやくような声で歌っている。
けっこうカッコいいんだけど、女の子にカバーしてもらおうと思うとなかなかむずかしいですねこれは。「♪右手がドリルで穴を掘る〜」ですから(笑)。それこそ篠原ともえくらいしか思い浮かばない。
新プッチとかがコンサートで突然やったらメチャクチャカッコいいんじゃないかと思うが、私の妄想ですね。ハイ。
・女の子ロボットソングまとめ
まあ、他にもアニメとかゲームとか声優ソングでありそうなんですがよく知らないんです。すいません。まあそのテのやつは「巫女みこナース」だけで自分にとっては100曲ぶん聞いた気がしますので。

とにかく、ロボットではなくてもいいけどテクノ歌謡を女の子アイドルが歌わなくなったら、この世は終わりなんです。現在、完全に女の子が歌うテクノ歌謡日照りです。
「宇宙人ソング」についても考えてみたいが、とりあえずピンク・レディーの「UFO」と、キララとウララの「センチ・メタル・ボーイ」しか思い浮かばなかった。ファンタジーソング? う〜ん、「リサの妖精伝説」。
(ロボット女の子ソング・終わり)
(04.1023)
・「鬼刃流転 孤高の天才剣士柳左近」 山上たつひこ(1990、マガジンハウス) [amazon]
NEWパンチザウルス連載。腕はたつが邪心を持つ天才剣士・柳左近が師・塚原右衛門に改造人間にされそうになり、裏切られたと怒って右衛門の右腕を切り落とし、流転の旅に出るというドタバタギャグマンガ。
あらすじを書くとギャグマンガじゃないみたいに思えるけど本当にギャグマンガです。
「血だるま剣法」(→感想)の解説に載っていて、なおかつたまたま古書店で売っていたので購入。本当に「血だるま剣法」のパロディ「蛇腹剣法」が出てきてた。時代劇もののパロディはさまざまあるが、上述のとおり、発端からして残酷時代劇画のパロディになっている。
内容は……山上たつひこにしては別にそんなに……と思う。呉智英はよくこんなの覚えてたなァと思った。
(04.1023)
【小説】・「駿河城御前試合」 南條範夫(1993、徳間書店) [amazon]
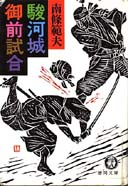
巷説寛永御前試合は虚構である。事実は、秀忠の次子・駿河大納言忠長の御前で行われた十一番の真剣試合が、その下敷きとなっている……。
実兄・将軍家光に反発し続け、最終的には切腹を申しつけられた忠長の、その狂気のうちに行われた真剣勝負の御前試合。その凄惨な行方を描いた連作短編集。山口貴由のマンガ「シグルイ」(→感想)の原案。
「シグルイ」がけっこう話題になっているので、連動して増刷でもしているんじゃないかと思ったら絶版らしい(不況は厳しい)。アマゾンでも古書扱いで、このテキスト執筆時点では品切れ。
で、図書館にあったので借りて読んでみた。これがなかなか面白い。
巻末の石井富士弥氏解説によると、本作は小説誌に、昭和31〜38年(1956〜63年)に断続的に発表された作品であるという。奇妙な剣技が連続する「忍法帖」的な1対1の対決を基本としているが、団体戦が主な山田風太郎と異なるのは、全11試合がお互いの因縁は何もなく、ただ対戦相手とのみ、凄惨な宿命というべきものがあるという点である。
晴れの試合がクライマックスになるのは映画「ロッキー」などが超有名だが、乱暴な言い方をすれば本作は11の物語のクライマックスがすべて同日の「駿河城御前試合」で行われる試合となる、と考えればよい。それだからこそ、7年間という長期の断続的な発表が可能だったのだろう。
それともうひとつ、風太郎忍法や「バキ」などと違う点は、ほとんどの試合が「勝てば万事OK」というたぐいのものではない、ということである。そもそも真剣で立ち会わねばならなくなったこと自体が不幸の結末である場合が多い。
たとえば風太郎忍法帖の、一作の中のバトルの中には「自分の力を試したい」とか「敵を倒したい」といった単純なものも盛り込まれ、それがチーム戦としてプロットを練り上げていき、最終的には虚無的な結末へ至るという形式が多い。あるいは格闘技モノにおける戦いの勝利は自己実現であって、それ以上でもそれ以下でもない。
だが本作においては、戦い合う斬り合うことそのことが宿命であって、ほとんどの試合が終わっても物事は何も解決せず、むしろ不幸になる者が出たりしてそれが腕が飛んだり胴体がちぎれたりという以上の「残酷」になっている。
だがまあ残酷にもいろいろあって、おそらく南條範夫という作家の作品にもいろいろなタイプの残酷があるとは思うが、1話1話が短く筆致もアッサリしているので、当時はともかく現在読んでもそれほど凄惨な感じはしない。
また、運命のいたずらとしか思えないやりきれぬエピソードの合間に、フリークスの復讐譚(「がま剣法」)、仇討ち的なもの(「身替り試合」)や、勝敗とは関係ないレベルの奇妙なエピソード(「被虐の受太刀」)、あるいはほぼ技の掛け合いの興味だけで話を進めたもの(「飛竜剣敗れたり」、「疾風陣幕突き」)など緩急を付けてある。「読者をイヤな気持ちにさせるためだけの残酷」を目指していないところ、虚無的な展開の中にわずかに勧善懲悪、因果応報的エピソードが混ざっているところが、エンターテインメントとしてうまいところだと思う。
・作品発表当時の時代背景(自分メモ)
石井富士弥氏の解説によると、吉川英治の「宮本武蔵」に代表される、剣技に対するきれいごとの修養的理解に対する反発が爆発し、単なる人斬りの凶器としての剣の技を描いた作品が出た。それが中山義秀「新剣豪伝」昭和29年(1954)、五味康祐の「秘剣」昭和29年、「柳生武芸帳」昭和31年(1956)、柴田練三郎「眠狂四郎シリーズ」昭和31年、「赤い影法師」昭和35年(1960)などであるという。
ちなみに山田風太郎の「甲賀忍法帖」が昭和34年(1959)。
前述したが、劇画「血だるま剣法」が1962年だから、こうした残酷性を伴った「剣豪小説ブーム」が、貸本劇画に影響を与えたと考えていいだろう。
「残酷時代劇映画」のハシリが「椿三十郎」(1962)だそうで、小説や劇画よりも若干ブームとしては遅いようだ。
それにしても、ラストに突然現れた「思い掛けずも現れた車大膳と称する不敵の剣士」(p471)っていうのの意味がぜんぜんわからなかった。本当に突然現れるんだよ。何だ。私の読みおとしか。伏線はなかったような気がするがなあ……。
(04.1020)
・「シグルイ」(1)〜(2) 南條範夫、山口貴由(2004、秋田書店) [amazon]
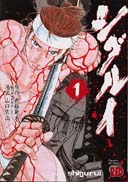
チャンピオンRED連載。
実兄・将軍家光に反発し続け、最終的には切腹を申しつけられた忠長の、その狂気のうちに真剣勝負の御前試合が行われた。出場剣士11組、22名のうち16名までが死に、2名が重傷を負ったというこの凄惨な試合の一番目に登場したのは、片腕の剣士と、盲目で跛足の剣士であった……。
原作は南條範夫の小説「駿河城御前試合」(→感想)。現在やってる藤木源之助と伊良子清玄とのエピソードは、原作の第1話「無明逆流れ」を思いっきり膨らましている。
原作もたぶん、風太郎忍法などの影響を受けたかなり超人的な技が頻出する作品だが、本作ではそれをさらに膨らませたり、ないエピソードをどんどん入れている。
いちばん極端なのが、岩本虎眼のキャラクター造形で、これはほぼ100パーセント、山口貴由の創作として見ていいのでは。それにしてもムチャクチャですねコイツは。
もともとの出自からして、勧善懲悪であったり、ウヨクチックなアイテムであったりを駆使しながら、実はその向こうにある狂気やエロスを描いていた山口貴由だから、この「駿河城御前試合」はピッタリの題材と言える。
ただ、私個人の好悪の判断で言えば、すさまじい迫力を持った惹きつける作品だとは言えるが、自分の好みの作品かどうかはまだわからない。「残酷」とは、常に物語のテーマが要請する場合と、ただ残酷なための残酷がある。これらは渾然一体で、必ずしも片方を否定するものではないが、どちらに重きを置くかは作家の気分次第。
今後、どっちに振れるかの予想がつかないからである。
実は、私は残酷ものは好きじゃないのである(「殺し屋1」とか、怖くていまだにページが開けない)。ただ、そこには私の好みであるしいたげられし者の復讐譚が含まれていることが多いので、まあ仕方なく読むこともある(「殺し屋1」がコワイのは、そういう単純な復讐譚の体裁を取りながらソレを解体してしまっているからだろうと自己分析する。イチの戦いには通常の「劇画」的なカタルシスはほとんどないから。ちょっとしか読んでないけど)。
「何かを失った者が、代わりに何かを得て反撃、もしくは復讐する」というエピソードは何も「残酷であること」とはまったく一致しない。最近、東京MXTVで「ど根性ガエル」を再放送しているが、平面ガエルだってこのパターンである(ひさしぶりに見た、平面ガエルとなったピョン吉がもう別世界の住人になってしまったピョン子をわざと手ひどくふるシーンには泣けたよ)。
別に、山口貴由に「オレの好みに合わせろ」と言っているわけじゃなくって(当たり前だが)、山口貴由は「『残酷』の必要性と不必要性(過剰さ)」をかなり意識していて、師匠筋の小池一夫なんかと比べるとほんの少し「過剰」の方に踏み出している作家だと思うのだ。だから、今後私ごのみの作品になっていくかどうかは、保留としか言いようがない。
最後に。単行本第1巻に「封建社会の完成形は、少数のサディストと多数のマゾヒストによって構成される」とあるが、私はそうは思わない。むしろ「構成人員全員が、サディストでありマゾヒストであることを強要される」と考えた方が正しくはないか。少なくとも原作「被虐の受太刀」はそれを表しているエピソードだと思えるのだが。
(04.1020)
【映画】・「DEVILMAN デビルマン」感想追記
・『デビルマン』は映画ファン必見だ!(山本弘のSF秘密基地)
(以下、引用)
>>ご注意
以下の文章はその性質上、映画『デビルマン』のストーリーに触れております。まあ、ストーリーを知ったところで、すでに最低の作品がこれ以上損なわれることはありえないのですが(笑)、念のため。
(引用終わり)
とにかく山本会長の映画『デビルマン』に対する情け容赦なさっぷりが横溢するテキスト。まず『映画「デビルマン」公式完全バイブル』を買った段階で、やっぱりすごいと思うなあ。
で、自分の映画「デビルマン」に対する心情をあらためて考えてみたんですが、映画界とか東映という会社の体質という、部外者にはよくわかんないものに考えが至ってしまうので、自分の中で無意識に思考にストップをかけていたように思います(笑)。
前にも書いたけど、最近の東映は「REDSHADOW赤影」と窪塚版「魔界転生」をリリースしたという次点で根本的におかしいと思うんだけど、何でそういうことになるのかがサッパリわからないので。
映画業界という特殊なものとしてより、企業としてわからないですよ。
よくハロプロファンの間でも、いろんなことに「何でこうしない!?」っていう文句は出るけど、それは個別的なことであって、大きな流れの中でのこまごまとしたことだと思うんですよ。
いい悪いは別にしても、「恋のテレフォンGOAL」とか、ちゃんとトータルに筋の通ったものを出してますから。
なんかね、でも最近の東映の映画の場合「どうせファンが何言ってもダメだろう」っていうあきらめの方が先に立っちゃうんですよね。
たとえば同じ東映でも、仮面ライダーシリーズとか戦隊モノとかでは、あそこまでダメにはならないでしょ。ライダーもいろいろ文句が出るけど、とりあえず最低ラインの基準がぜんぜん高いわけで。つくってる部署自体が違うんですかね……。
それと、まだ比較的製作工程がわかる気がする「マンガ」と比べても、東映の特撮映画は設立過程において不可解なことが多い。たとえばマンガの原作者と作画者の組み合わせとかに、そんなにとことんヘンなものはないですよ。
実際、マンガのデビルマン企画でここまで妙なものは皆無ですし。
だけど映画の「デビルマン」って、以下はもう完全に勘だけで書いてますが、ものすごい利権がからみあいすぎて、船頭多くして船が山に登ったんじゃないかと。で、さらに「REDSHADOW赤影」を出した実績から考えても(しつこい)、時代感覚のある人が船頭として集まっているようには見えないんですよね。
(しかし、金もうけしたいんだったらこのプロットで三部作とかにするよな、とも思ったりする)
まあ、私にとっては言ってみれば「サラリーマン的なあきらめ」しかないんですわこの映画に。
(でも、もしそれで責任のほとんどが監督にあったらそれはそれでコワイ話ではある)
それともうひとつは、私は「平成ライダー」、「CASSHERN」、それとマンガでは「最終兵器彼女」にかなりマイナスの意味でショックを受けてまして、しかもそれが時代の趨勢だと思っているんですよね。
確かに、映画「デビルマン」にも「CASSHERN」的な要素は出てきますが(デーモンが完全に「異形の弱者」としてしかとらえられていない点など)、それでもまあいちおう最後に明と了の対決まで持っていったので、ホッとしたというのはある。
これ、「CASSHERN」的な感覚で脚本書いたら、明と了は対決しないで終わるとか、明らかに了のやってることが正しいとしか思えない状態でラストに持っていくとかになってたと思いますんで。
なんかそういうですね、「CASSHERN恐怖症」的な面は私にはありますね確実に。
マンガの映画化は、基本的に好きなんですけどね。まあそういう甘さも私の評価に出てしまったのかもしれん。
【映画】・「DEVILMAN デビルマン」 監督:那須博之、脚本:那須真知子(2004、東映)感想
(04.1019)
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2004、テレビ東京)
10月17日放送分。
公式ページ。
いつもは、録画をざっと見返しながら感想を書いているのだが、今回は初見だけで感想を書いてみる。
まずゲームのタイトル忘れた。あ、ネット見て思い出した。
よ〜く見てみて 観察力バトル。
ニセモノと本物を遠目で見分けたりするゲームですよ。今回は2チームに分かれてるから連帯責任性は薄まった。
前回、プレッシャーで紺野が泣いてしまったのがもう1年近く前だったので、時の流れの早さに衝撃で吐きそうになった。
・「どれがニセモノの陶器か?」(正しいタイトルではない)
まあ、序盤戦。でも、テレビで見ててもどれがニセモノかわからなかったよ(ウド鈴木のポカンとした表情で)。
・「二人羽織をやってないのはだれだ?」(正しいタイトルではない)
「亀井が後ろで動いてた」というのと、後ろ側に回っていた道重に見せ場がゼロだったのが印象的。
・「すごい芸を持っているのはだれだ?」(正しいタイトルではない)
ガイジンタレントさんが、黒いマントを羽織って複数登場、だれがすごい芸をもっているのか当てる。
実際の芸披露のとき、(基本的に「娘。」のリアクションは「すご〜い!」とか「なんでー!?」とか安心して見ていられるものなのだが)「たいしたことないじゃん」的な顔の石川がたまたま写っていた。っていうか、もっと「すご〜い!」って顔のショットなかったのかな。
コント「公園通り三丁目」。
亀井、男の子のかっこうをしてもまるで男の子に見えない。
「女の子が少年のかっこうをする」中性的な美しさというのは、もうずーっと前、戦前から指摘されてるらしいけど、「男の子のかっこうをしているのに、女の子のようにしか見えない」状態というのはまだじゅうぶんに愛でられているとはいいがたい。
なぜかというと、男女のファッションの差があまりなくなってきて、「このかっこうをすれば男、女」というキメのスタイルが減少してきていることが「まだ女の子に見える」という中途半端なかっこうを現出させることになったからだと思う。
だからなんだっつーと、何でもありません。
細木和子みたいなキャラは、苦手なのでぜんぶ早送りしました。
それにしても、細木和子(本物の方)を復活させてテレビで大人気になるなんて……そりゃ日本にカクメイも暴動も起きるわけねェよ。橋本治はその辺に絶望したらいいと思う。平岡正明は絶望しちゃダメ。
「モーニング娘。 ラッキー7オーディション」の告知やら、四期のオーディション時のコメントやら。
個人的には「オーディションに受かる前」というのは実は興味がない。だって、アイドルっていうのはオーディションに受かって、パッケージングされてなんぼだから。
これは「青田買い」を楽しみにしているアイドルファンの人たちとは意見が分かれるだろうけど。
売り出しの路線が変わるといかに変わってしまうかは、ちょっと前なら坂上香織、最近なら伊藤かなや熊切あさみ、あるいはバラドルになろうとして急にがっつき始める元アイドルなんかに顕著でしょう。
「アイドルの人生観、そのアイドルの伝説」は、オーディションに受かってイメージが確定し、パッケージングされて売り出されてから帰納的に割り出されてくるものだから、過去をさかのぼっても個人的にはあまり意味がないんだよね。
まあ石川梨華はどこに行ってもある程度何とかなってたとは思うけど。
・地球戦士W(ダブルユー)。
もう完全に黒人の司令官みたいな人のイメージがわかんなくなってきてるな。
防災訓練の続き。火災のときの逃げ方とか、暴風雨を体験できる部屋に入ったりとか。
あまりにも立て板に水でしゃべる、防災の説明をするおねえさんを微妙にいじろうとする加護が面白かった。ありゃいじりたくなるよ。
ああいうおねえさん、友達同士で酒飲んでるときとか、どういうぶっちゃけ方してるのかちょっと気になるけど3秒後にはどうでもよくなった。
・HPH。
キャメイのゲストは「ロボキッス」を出したW(ダブルユー)。「顔に乗せたマシュマロを、落とさないように食べる」というゲームに興じているコドモたち(加護、辻、亀井)を見ていて、笑っているうちに、これは彼女たちのせいではなく自分自身の責任として、奈落の底に落ちていくような虚無感、絶望感にとらわれていきました(最強伝説黒沢的絶望ね)。
そういう意味ではアイドルはだれにでも、どんなときにでも元気をくれる存在ではないのですね(←何を言ってるんだこの男は……)。
まあ、だからこそ宗教とか哲学とかキャバクラとか井上和香とかがあるんだろうけど。
加護、胸の谷間がチラッと見えてましたよ。こういうのにいちいち反応する自分にも絶望した。何でもない週刊誌に出てる女に欲情してるムショ暮らしか私は(本当に「チラッ」としか見えないんですよ)。まあ、最近のテレビがエロを排除しすぎてるんだよな。
罰ゲーム。まずいお茶を飲まされる。矢口はこういうリアクションはうまくない方だと思う。こういうのはもう安倍さんしかいないんですよ。安倍さんばんざい!!!!!
・前回の放送
(04.1018)
「つれづれなるマンガ感想文2004」もくじに戻る
「つれづれなるマンガ感想文」10月前半
「つれづれなるマンガ感想文」11月前半
ここがいちばん下です
トップに戻る