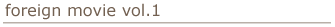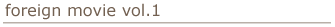ナック
リチャード・レスター監督、1965年の作品。同年カンヌ国際映画祭グランプリに輝いた作品。60年代のポップテイストが満載。当時のロンドンの様子も見逃せない。思わず「ぷっ」っと笑ってしまうような、映像の巻き戻し・反復・早送り・停止などがとってもおもしろい。意味無く出てくるテロップだとか。街の人々の声が若者達の皮肉をこめていたり、当時の時代背景などを物語っていたりする。そういう小憎い演出が好き。一つ気になるのは、リタ・トゥシンハムがあんまりかわいくないことだったりして。女の子にモテるコツは時と場所。なんて言ってたって、偶然やってくるものなんだよね。実際。