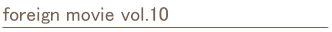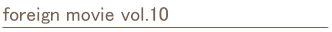|
アルファヴィル
Alphaville,une Etrange aventure de Lemmy Caution
監督・脚本 / ジャン=リュック・ゴダール
製作 / アンドレ・ミシュラン
撮影: ラウール・クタール
音楽: ポール・ミスラキ
出演: エディ・コンスタンティーヌ、アンナ・カリーナ、ラズロ・サボ、エイキム・タミロフ 他
1965年 / フランス
SF、ハードボイルドを用いた近未来のストーリー。言葉の否定・記号化・個人の抑圧、つまり共産主義への批判をしながら愛の言葉が世界を救うと説く、愛とか脱出はおいておいてもゴダールぽい映画。ただ共産主義自体を私は正直それほど理解してないし、その無気味さに何か特別強く疑問を持っているわけでもなく、しかしそういうスタンスで見ていても当時最先端の建築デザインが多く出てくるのは楽しかったし、モノクロのアンナ・カリーナはかわいくて、プールで処刑されその後水着の女性がシンクロをするシーンはのん気で面白かった。
|