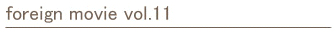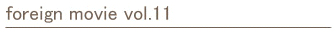|
自転車泥棒
Ladri di Biciclette
監督・製作 / ヴィットリオ・デ・シーカ
脚本 / チェザーレ・ザヴァッティーニ
原作 / ルイジ・バルトリーニ
脚本 / チェザーレ・ザヴァッティーニ、スーゾ・チェッキ・ダミーコ
撮影 / カルロ・モンテュオリ
音楽 / アレッサンドロ・チコニーニ
出演 / ランベルト・マッジォラーニ、エンツォ・スタヨーラ 他
1948年 / イタリア
ネオ・リアリズモ。映像で認識できるすべてが当時のイタリアの現実ではない。けれど俳優らしからぬ素人俳優たちはその匿名性ゆえに個人ではなく全体を認識し、意識することができる。戦後の殺伐としたイタリア、やっと職を見つけた父親は仕事のために手に入れた自転車を盗まれる。悲惨な街、悲惨な生活、生きることという現実と真実。ロッセリーニ『無防備都市(ROMA, CITTA, APERTA)』(1945)、『ドイツ零年(Germania anno zero)』(1947)と同様の絶望感。こめられたメッセージ性よりも強い寂寥がある。
|