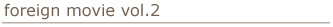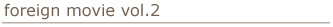|
手
監督、脚本、原案 / イジィ・トルンカ
音楽 / ヴァツラフ・トロヤン
撮影 / イジィ・シャフアージ
1965年 / チェコ
花を愛し、花の為に植木鉢を作っているアルルカンの家に突然「手」が侵入してくる。アルルカンは小さなもののために、小さな花のために何かが出来る生活が幸せだった。大好きな花があれば他に何もいらなかった。「手」は強制的に「手」の像を作らせる。小さなものすら守れない。自分の守りたいものが守れない。アルルカンは涙を流す。像の完成後、その花が頭に落ちてきてアルルカンは死ぬ。「手」が象徴するのは言うまでもない。この作品を完成させ、短い「プラハの春」が終りを告げた翌年の1969年にトルンカはこの世を去った。トルンカはどんな気持ちでこの作品を作ったのだろう。あまりに重く、痛い、トルンカの遺作である。
|