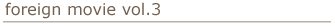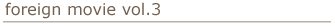|
親指トムの奇妙な冒険
監督・デザイン・脚本・編集 / デイヴ・ボースウィック
アニメーター / デイヴ・ボースウィック、ブレット・レイン、ヘレン・ヴェウズィ 他
美術・衣装・メイク / ザ・ボレックスブラザーズ 他
キャラクター・モデル / ジャスティン・エクスリー&ジャン・サンガー
1993年 / イギリス
ついに見ることが出来たこの作品は、期待以上に面白くて私を裏切らなかった。想像と少々違うストーリーだったけれどデイヴ・ボースウィックの熱の入れように惚れ込む。実写とパペットの作品なのだけど、人間の細かい動きもすべてアニメーション。たしかにグロテスクで子供受けはしないと思うけれど、それでもパペットがこれだけかわいらしいとかわいらしく思えてしまうもの。親指トムのかわいらしさといったらそれはそれは私のストライクゾーンど真ん中という感じで、声の演出もまたこれがかわいくて。危機一髪を乗り越える姿やトムの優しい性格が心に残る。トムの世界は危険がいっぱい。私はずっとずっとトムの味方よ。
|