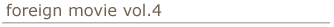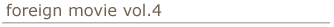|
快楽殿の創造
Inauguration Of The Pleasure Dome
原案・監督・編集 / ケネス・アンガー
音楽 / E.L.O.
撮影地 / ハリウッド
出演 / サムソン・ド・ブリエ、カメレオン、ジョアン・ホイットニー、アナイス・ニン 他
1954,1956,1958,1960,1978年 / アメリカ
繰り返し改訂がされ多数のヴァージョンがあるようだけど、見たのはアンガーがロサンゼルスに帰ってから作られた最終版。ドラッグを意識するようなサイケデリックな映像。アンガーの作品は思わず我を忘れて画面を見るような、そんな引き込み方をされる。複雑な画面の作り方にも圧倒。アンガーの映画はすごい。一生に一度でもこういう映像を見る事が出来て良かったと思える。
|