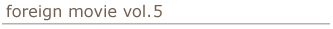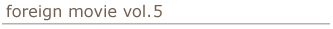|
シュッ・シュッ
TCHOU-tchou
監督・スクリプト / コ・ホードマン
キャラクターデザイン / スザンヌ・ジェルヴェ
アニメーター / ジャナ・B・スバール
編集 / イブ・ルダック
音楽 / ノーマン・ロジェ
録音 / ロジェ・ラムール
リレコーディング / ジャンピエール・ジュテル
製作管理 / ジャクリーヌ・マルキ
プロデューサー / ピエール・モレッティー
1972年 / カナダ
合計3,000個のブロックを使用し、ブロックそのものとブロックに描かれたアニメが動く。カラフルなそのブロックはオランダ製らしく、そんな所に女の子の食指は動くというもの。コ・ホードマンのアニメはきっと子ども向けに作られるものが多い。大人が見るアニメのように、テーマ重視だったりするわけじゃない。大人が見たら、きっと大部分忘れてしまう内容かもしれない。けれど子どもたちの心には、青や赤や緑のブロックが楽しい記憶を蘇らせるのかもしれない。
|