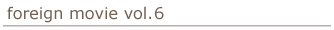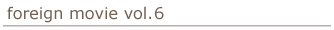|
「ぼくらと遊ぼう」シリーズ "お魚の話"
K Princeznam se necucha
監督 / ブジェチスラフ・ポヤル
原案 / イヴァン・ウルバン
脚本 / イヴァン・ウルバン、ブジェチスラフ・ポヤル
美術 / ミロスラフ・シュテパーネク
音楽 / ウィリアム・ブゴヴィー
撮影 / ヴラディミール・マリーク
製作 / クラートキー・フィルム・プラハ
1965年 / チェコ
"悲しい目のお魚は魔法にかけられたお姫様なんですよ"と大きなクマちゃんに言われた小さなクマちゃんはそれを信じてお姫様(お魚)を救う英雄になろうとする。焼き魚にした後だったけど。食べられてしまったお魚の骨を見てポロポロ涙を流す小さなクマちゃん。大きなクマちゃんは"お姫様なんて言ってる歳じゃないでしょ"としかる。時々感覚が微妙に子供じゃなくなるのが好き。
|