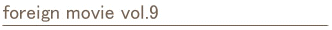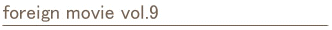|
ジュリオの当惑
La Messa E` Finita
監督・脚本 / ナンニ・モレッティ
製作 / アキーレ・マンゾッティ
原作 / サンドロ・ペトラリア
脚本 / サンドロ・ペトラリア
撮影 / フランコ・ディ・ジャコモ
音楽 / ニコラ・ピオヴァーニ
出演 / ナンニ・モレッティ、フェルッチョ・デ・セレサ、エリンカ・マリア・モドゥーニョ、マルガリータ・ロサーノ、マルコ・メッセリ 他
1985年 / イタリア
小さな島からローマ近郊へ赴任してきた司祭ジュリオの奮闘。ジュリオ役は当然ナンニ・モレッティ。真面目なジュリオが戸惑うのは自分本位な人々の行動。悩みながら先へ進むジュリオを止めたのは母の自殺。人の話を聞き他人の欠点を愛嬌に変え孤独は決して自由ではないと二人で自由をつかむのが幸せだと。少し恥ずかしくて斜にかまえてしまうような問題を愛にあふれたユーモアで軽快に描く。教会の祭壇で「人生は素晴らしい」と涙を浮かべて話すジュリオと人々の幸せそうなダンスと音楽。そんなラストはとてもナンニ・モレッティらしくて彼の映画が好きな理由のひとつ。
|