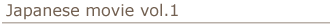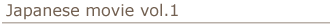|
G線上の悲劇
製作・構成・演出・撮影・アニメーション / 久里洋二
音楽 / 一柳慧
1969年
一柳慧の音楽に久里洋二がアニメを考えた作品。この一柳慧の音楽がすばらしくて、私は出だしのヴァイオリンの音から大好き。それは久里作品と同様、絶壁に追いつめられていくような感覚と、突然場面が変わって狭い何もない部屋に閉じこめられる感覚。ゆらゆらとする線が音と一緒に突き進む。途中途中に出てくるCGも、その、無機質さを象徴するように感じられる。何度見てもすごいと思う。一柳慧のこの音楽のイメージはまさに久里洋二のアニメ。久里洋二以外にこんなもの作れなかったような気がする。そういえばロス・アプソン店長、山辺圭司もこの作品に興奮したと書いていたような。
|