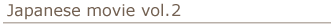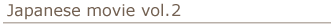|
SAWADA 青森からベトナムへ
ピュリツァー賞カメラマン沢田教一の生と死
監督 / 五十嵐匠
製作 / 小泉修吉
撮影 / 堀田泰寛
音楽 / 寺嶋民哉
録音 / 中山隆匡
出演 / 沢田サタ、ケイト・エェップ、根津甚八、森篤夫 他
1997年
カメラマン沢田教一はベトナム戦争の報道写真「安全への逃避」でピュリツァー賞を受賞、内戦のカンボジアで撃たれ、1970年に亡くなった。家族や友人のインタヴューを通して沢田教一の一生をふりかえるドキュメンタリー映画。私は彼のことを知らなかった。ピュリツァー賞を知っていても内容や事情に詳しくなかった。一枚の写真から彼の被写体に対する敬意と真摯な態度が見える。写真には何も言えなくなる必死さ、無念さ、やりきれなさがある。死に物狂いでいい写真を撮ろうとした。なんとなく、の写真が流行ることもある。それはそれでいい写真もあるけれど、同じ青い空を写した写真は、決定的に違う。
|