【雑記その3】無題
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2005、テレビ東京)
・「極道兵器」全3巻 石川賢(1997〜98、リイド社)
・「でろでろ」(4)〜(5) 押切蓮介(2005、講談社)
・「明日色の空」 このどんと(2005、久保書店)
・「魁!! 男塾」全34巻 宮下あきら(1986〜1992、集英社)
【雑記その2】・やっとamazonで「と学会年鑑Rose」 と学会:著(2005、楽工社)取り扱い
【雑記】・「鶴岡法斎のエログロ・ハイセンス Vol.3」〜9/18 於:NAKED LOFT
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2005、テレビ東京)
【雑記その3】無題
事情があって、OSを9からXに変えたんですよ。
そうしたらすべてが使いにくくなってしまって……。
何かこう、文明社会に嘲笑されているような……。
いや、実際されていると思うんだけどね。
きっとどこかに超巨大なコンピュータがあって、人々を操っているんですよ。
パソコンはその端末です。
あと、もつ鍋ブームとか、ああいうのも端末だね。
長澤まさみとかも。
世知辛いねぇ〜。
このテキストもなんだか書きにくくてさあ〜。物理的に。ことえりのバカ野郎。
ところで、「と学会年間Rose」ですが、またamazonで「在庫切れ」になってしまってまして。
おかしいなあ……ホントに取り扱っている時期、あったんだけどなあ。
結果的に、わたしウソつきになってしまいましたよ。
話は変わりまして、「いいとも」の「年内終わるんですか」野郎の問題なんですけど。
あれって「ロンパールーム」の「くまのぬいぐるみ事件」という都市伝説を、テレビ番組が(フォローするために)追認したってことですよね。 そういう意味では、実にネタとマジが交錯した事件ではあったと思いますね。
私個人は、ああいう生放送の番組で、ああいうことをするのはマイナスの意味で人心を惑わすという意味で非常に感心しません(同じく、東京タワーに登っちゃうやつとか)。
「笑っていいとも!」でなくても、それは池田小学校の事件でもそうだったけどね(殺人事件と一緒にするのはどうかとも思ったけど、ものすごく大雑把に言って、構造的には同じだから)、基本的に「むちゃくちゃなことをやる人」に合わせて人間のシステムってできてないんですよ。
っていうか、構築が不可能なんです。
そういうことを人々に気づかせる、というのが、パフォーマンスとして有効だった時代というのは確かにあるんだろうけど(文字どおり「パフォーマンス」とか「ハプニング」とかが流行った時代ね。だからもう30年以上前かな?)、今はもうそういうのはぜんぶ織り込み済みの時代だから。
だから何をやっても「ネタ」というオブラートでからめとられるし、私はある程度はそれでいいと思ってるけどね。そこから、穏当な方法でいったい何をアウトプットするかというのが現代の勝負なのであって、ハプニング的行為っていうのは現在ではそれだけでは一種の度胸試し以上の意味を何ら持たないから。
ただし、「増刊号」をチラッと見たらエンディングでくまのぬいぐるみが映ってたんで、たぶん放送したのだろうと思うけど、そういう送り手の「ネタ化によるハプニングの無効化」を、「そういうことをやってやろう」という目立ちたがり屋がどこまで理解してくれるか、というのはある。
オウム事件もそうだったけど、人間というのは具体的に働きかける権限を持っている人がちょっと理解しがたいほどバカなものだからね。
だってねえ、たとえば平日のお昼の生放送で、タモリが暗殺とかされてしまったら、それこそ本当に無駄に人心に不安を与えるからねえ。
「みんなの善意で形成されている場」ということを、なんだか生徒会長みたいな物言いだが、よく考えてほしい。だれに言っているのかわからんけど。
ところで、ロンパールームのクマ事件なんだが、初代おねえさんのうつみみどりが「本当にあった」って発言してるらしいけど、あの人のことだからどこまで本当かはわからないよ。わりとネタ的にほら話する人だからさー。「ごきげんよう」とかでくだらないことをよくしゃべってる。
あーつまらないことを書いてしまった。
おわびに、エヴァンゲリオン世代のみなさんに「なんにもかかってないエヴァンゲリオンの替え歌」をお送りします。
(以下、歌)
おーだんほどうを わたるときには
しょーおーねんよ マンガ読むーなー
パンチ佐藤が 今日も 目をぎょろつかせ
魚河岸の レポートを 得意げに してた
近所の スーパーの 屋根の上に 立つのは
な〜ぜか ボウリングのピン 昔ボウリング場だったから〜
だけど 今はスーパーになり ばばあが群がる
だけど さらに哀しいのは このスーパーも閉店予定〜
バ〜ンコクの 柔道選手
どこか 三瓶に似ていた
「三瓶に似てるね」と言ったら
みーんーな 忘れてたよ 三瓶
「三瓶でぇす」と やってみたけど
わーすーれてたよ
やっぱり 三瓶!
(↓へんな何言ってるかわからないコーラスみたいなやつ)
10円じゃ〜〜
何も買えない〜〜
だからって〜〜
20円でも……………………
(間奏)
「三瓶でぇす」とやってみたけど
わーすーれてたよ
やっぱり 三瓶!
(05.0928)
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2005、テレビ東京)
9月25日放送分。
公式ページ。
あの……そろそろ感想書くのやめていいですか……。
そもそもが、モーニング娘。はここ半年間くらいかけてテレビと乖離し続けてきたと思います。テレビを利用してのし上がってきたグループだと思うんですが、もはやそのおもかげはありません。
矢口が脱退して、「やぐちひとり」などで「背負うもの」がなくなったときに、その乖離は決定的になったと思います。
ですんで、もう現状のハロモニ。は全員が美少女クラブ31になっても何ら変わりないところまで落ちてしまっていると思うんですわ。
また、どういうわけか企画も恐ろしいまでにレベルダウンしてます。まあ、もともとがお昼のまったり番組なんでとんがったところはなかったにせよ、ロケもののデート企画が始まって以来なぜかスタジオものの低レベル化も看過できないものになりつつあります。
今回「安田大サーカスとゲーム」というものでしたが、とにかく「安田大サーカスとゲームをする」という必然性が皆無のうえ、ゲーム性もいちじるしく低い。安田大サーカスはものすごくがんばってましたが、逆に言えば芸人のがんばりがあそこまで明らかになってしまうのはゲームが薄い証拠でしょう。ちょっと企画そのものに軽い怒りすら覚えましたよ。あれじゃ出演者全員かわいそうです。
コントはリニューアル。駅員(石川、辻、亀井)と売店のおばちゃん(吉澤)を中心として、メンバーが出てきてはハケる、というふうになりました。これもまあ、初回第1回から構成としては何ら変わってません。トホホ。 まあ、実は久住の妙にテンションの高い幼稚園児とか、「ミニスカなのにヒッピー風」というよくわかんないファッションの三好とか、ちょっと笑った部分もありましたがこれで笑ってちゃいけない気がしてきました。
マジックレストラン。Dr.ZUMAというマジシャンは、何か懐かしい、バカバカしさを漂わせたマジックで、それでいていわゆるイリュージョンではないというのが気に入りました。あ、最初のテレパシーは「古畑任三郎」でやってたトリックですな。そんなところも好き。一瞬目玉が取れちゃうとか。
「毎度ありぃ」。亀井は体操服が恐ろしく似合うなあ、と思いましたがそれで良しとしてはいけない気がしてきました。
放送時間も短くなるそうで、いったい何が、どこが悪いのかわかりませんがもう構造的に面白くないスパイラルに入ってしまっていると思います。
きっともう何もかも終わりなんですよ。私以外の人間が幸せになるなら、勝手に幸せになるがいいさ。
・前回の放送
(05.0925)
・「極道兵器」全3巻 石川賢(1997〜98、リイド社) [amazon]
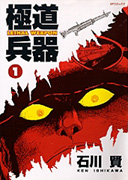
COMICマイティ、漫画サンデー連載。暴れん坊で血を見るのが大好きなヤクザの組長の息子・岩鬼将造は、海外で傭兵稼業をしていたが、父親の死をきっかけに日本に帰国。
世界征服を狙う「デスドロップマフィア」と戦うことになり重傷を負うが、いろいろあって身体に兵器を内蔵した「極道兵器」として蘇る。
ここ(ビバ! ダイナミック)にほとんどすべて書かれちゃってるんで書き加えることはあまりないんですが、私が「メチャクチャ」というときの「メチャクチャ」とは何か、ということに関して複数名から疑問・質問いただいたのでその辺の説明をしようと思う。
「石川賢」を表現するのに、私はよく「メチャクチャだ」という言葉を使うんですが、「言うほどメチャクチャじゃないじゃないか」という意見も聞く。この見解の相違は何かというと、石川賢が「マンガ」としての体裁はかなり忠実に守っている点から来るのではないかと思う。
永井豪と石川賢の作品の個性を論じるのも、いったいどの作品にだれがどの程度関わっているのか、作品を読み込むだけではわかりづらいのでむずかしい問題ではあるが、確かに永井豪の方がその「投げっぱなし度」は高いように思う。
逆に言うとダイナミック作品の中で、アナーキーながらもまとまっているものに石川賢が関わっているのか? と考えることもできる。
ただ、永井豪の場合「メチャクチャ」というより「いいかげん」という言い回しの方がふさわしい気がするが……。
3巻巻末に載っている読みきり「真・極道兵器」を読むと、石川賢のメチャクチャさというのは「B級映画的なメチャクチャ」だということがよくわかる。要するに、どんなにブッ飛んでようが1時間30分くらいでキッチリ終わるメチャクチャさなのだ。
主人公がムチャだったり、兵器がムチャだったり、戦いはムチャだったりする。しかし、キャラクターの信念が通っているから、作品の中に「いったいどこに連れていかれるのだろう」という不安感は皆無なのだ。だからこそ、ブッツリ終わっても読者はイライラしたりはしない。少なくとも「あるべき最終回」は、主人公の信念が貫徹されることになるであろうことは予想できるから。
とくに「真・極道兵器」は、やくざ映画のパターンを逆手にとってクライマックスの驚きが演出され、なおかつラストもまとまっているという点で、石川賢のいい意味での「B級映画感」が非常によく出た作品になっていると思う。
なお「極道兵器」のキャラクターのメチャクチャさについては、主人公が「仁義なき戦い 広島死闘篇」 の千葉真一演じる大友勝利がモデルだというだけでわかっていただけると思う。
「仁義」でも屈指のメチャクチャキャラを主人公にしてSFアクションに仕立てようというのだから、ワクワクしないはずがないのであった。
(05.0924)
・「でろでろ」(4)〜(5) 押切蓮介(2005、講談社) [amazon]
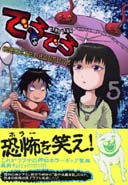
週刊ヤングマガジン連載。霊感体質らしいヤンキー少年・耳雄が出会う奇っ怪な妖怪の数々。
いや〜正直、4巻の大西祥平氏の解説がすべてを言い表していて、書くことがないんですわ。「ああ、俺は今、漫画を読んでいる! 漫画を堪能している!」というエクスタシーが存在する、というのはもうまったくそのとおりで。
ウマイこと書こうと思っても浮かばないんで、好きなエピソードの羅列で終わらせていただきます。
・4巻
「マロンさんが来る!!」
携帯で来訪を告げる都市伝説的妖怪「マロンさん」。ラストのコマのマロンさんの無念の表情がすごくカワイイ。
「ラクガキカキカキ」
「電話をしている最中にやってしまう無意識の落書き」という着眼点だけで感心。
「連打だ! クリスマス」
最後には耳雄に同情してしまう妖怪がいい。
「わらわら新成人」
「暴れる新成人」をネタにしているだけでも大爆笑してしまいました。爽快。
「ホームにて」
「じらされ地獄」
両方とも、あるあるネタが秀逸。
・5巻
「原宿スキスキ!!」
人々が珍妙な格好をして歩いているため、妖怪も素でいられる「原宿」という街。ケッ作。
「ホラー先手必勝」
ホラーにおけるあるあるネタと、耳雄のバイオレンスは相性がいい。
「うしろ髪」
わかっていてもホロリとしてしまう。そんな泣かせ系も好きです。
・1〜3巻の感想
(05.0924)
・「明日色の空」 このどんと(2005、久保書店) [amazon]
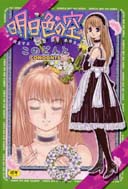
成年コミック。出典不明の短編集(初出が書いてないんだもんよ)。
「明日色の空」、「玄界灘を越えろ!!」シリーズ、「殺戮都市」、「魔性の森」、「ミッドナイト・ゲート」、「ミッドナイト・ゲートII」、「羽衣天女」収録。
ハートフル少女マンガ風の表紙にダマされてはいけない。内容は鬼畜、鬼畜、ギャグをはさんでこれ鬼畜である。
表題作「明日色の空」は、けなげな美少女が坂道を転げるようにエロ的に不幸になっていくというものだし、「ミッドナイト・ゲート」は女子高生同士の納得ずくレズSMプレイだが、「すべて罠だったのです……」みたいな妙な後味で終わる。
「玄界灘を越えろ!」が唯一、ギャグっぽい短編連作である(でも女の子が縛られる緊縛モノ)。
私・新田五郎が、肉体改造モノが大の苦手であることは多方面に有名なことではありますが、なぜかこのどんとだけはけっこう読んでいる(この単行本にもよく出てくるんだけど)。他の作家の作品ほど気持ち悪いとかも、なぜかあんまり思わない。
それは、このどんとの描く鬼畜路線がかなり「世の中に対する恨みつらみ」という方向でまとまっているからだ。
ちょっと変わったエロマンガを読んでいて何とも不安な気分になる場合というのは、「性欲」というものが制御不可能な何かであり、肉体的なエクスタシーは「たまたま人間の肉体がそのような機能を持っているから」にすぎず、どんどんさまざまな方向へ拡散していくという自己崩壊の恐怖があるからだと思う。そういう「際限のない拡散」が肉体そのものを変容させる方向に進み、それが不安感を煽るというのは理解していただけるかと思う。
その点、このどんとの作品の方向性というのは、肉体変容とかも取り扱われているが明確だ。それはわりとストレートな世の中に対する恨みで、当然「女の子にモテない」ということも入っているだろう。「どうして女の子にこんなヒドいことをするか」というと、たぶんモテないからだと思う(モテてたらすいません)。
コレが「何もかも満ち足りているのにひどいことをする/される」となると、変態のステージが何段階も上がってしまうわけである。世に非道な犯罪は多いが、この間の鬼畜調教路線で事件を起こした「王子様」に対するおおかたの反応も「女に不自由しているわけじゃなし……」というものだろうし。
というわけで、当然少女マンガチックな表紙イラストも、わかりやすい「悪意」の表明である。やっぱり世の中、わかりやすいのがいちばんである。
「非モテ」とか言って理論武装するよりは、エロマンガでも読んでストレス解消した方がいいと思うのは私だけであろうか。
もちろん、非道なことは想像の中だけでやってください、ということなのだが。
作者のこのどんとについては、80年代のロリコン・美少女ブームを経たHマンガ史において、おそらく森山塔の鬼畜路線をより発展して拡大させたという恐るべき功績がある。しかもそこにはふたなり、スカトロ、強制レズ、肉体改造などの変態満漢全席であったことに加え、SF的設定を駆使して独特な世界観ができあがっており、なおかつマンガとしての完成度が高い。
これは作者の代表作である「奴隷戦士マヤ」[amazon]が何度も何度も再販を繰り返していることからも証明されよう(「いつまで経っても終わりそうにない」という難はあるのだが)。
あ、「スーパーロイド愛」[amazon]も再販されてるね。
「奴隷戦士マヤ」の連載が確かミヤザキ事件の前、確か87、88年頃のことで、なんと普通のコンビニに「マヤ」の総集編が置かれていたのである。しかも、それがおそらく美少女マンガ史上初の鬼畜ぶりだったのだ。当時は驚いたもんである。
(05.0923)
・「魁!! 男塾」全34巻 宮下あきら(1986〜1992、集英社) [amazon]

週刊少年ジャンプ連載。日本全国のゴンタクレばかりが集まる絶対封建制、ムチャなシゴキが横行する私塾・男塾。
そこに集った男たちの、奇想天外な戦い。
……あらすじをまとめようとしたら、変になっちゃったよ。文庫版第1巻のamazonのレビューのひとつが面白い。
>>作者はそれほど深く物事を考えていません。
うん、それに尽きるよなあ。私もそう思う。しかし、どうにも喉に引っかかった魚の骨のごとく、私の心に微細な違和感があることも否めないので、ちょっくらその辺のことも含めて、なおかつ2005年の現時点から後出しジャンケン的ではあるが思うところを書いてみたい。なお、「民明書房大全」[amazon]をまだ読んでいないので、見当違いの予想を書いていたらご容赦願いたい。
・導入部:ギャグ編
当初、本作は過去の応援団ものや体育会系もののギャグの系譜として始まった。どの程度の構想があったかはわからないが、このままこの路線が続けば同じ作者のコメディ色の強い作品「ボギーTHE GREAT」のようになってもおかしくなかったと思う。
ギャグの形式としては、毎回まいかい男塾の一号生たちが、塾の伝統である妙な試練に付き合わされてヒドい目に遭う繰り返し。読み返してみると「撲針愚(ボクシング)」のような妙な競技を次々とやらされるところまで「ギャグ編」と考えると、ジャンプコミックスで3巻ぶんくらいはやっている。意外に長いのである。
「深く物事を考えていない」ことには同意するが、私個人は「戦前のシゴキ教育をカリカチュアライズした私塾」という設定にまったく意味がないとは、実は思わない。ジャンプコミックスの作者コメントでは「厳しかった父が江田島平八のモデル」と書かれているし、作者が80年代当時の軽薄短小気分にイヤ気がさして、「心のふるさと」を過去に求めていたことは間違いないとは思うのだ。
ただし、その「心のふるさと」が何なのかがサッパリわからない。
少なくとも、軍事教練などをやっていた時代でもないだろうし、「バンカラ」をモットーとした旧制高校でもないようだし、同時期の体育会系でもないようである。
ここら辺のバランスはいくら考えてもわからない。まあ、本当に何を考えてもムダなのかもしれないが、ものすごく単純に言えば映画「網走番外地」の、シリーズ化されるごとに薄れていく最果ての刑務所の受刑者の悲哀と、それと反比例して強調されていくお話の飛躍、そのあたりが宮下あきらの心のユートピアなのではないかと思う(「激!! 極虎一家」はだいたいそんな話であった)。
・驚邏大四凶殺
関東豪学連との戦い。4VS4マッチである。どんどん富士山の上に登っていくのだが、大人数でないと支えられない巨大鉄球を押し上げていかないといけない。
これは、1対1の勝負になったときに仲間が助けに入れない(鉄球から離れると支えていられなくなる)という競技上の意味あいがあったのかもしれない。あるいは「試練」を強化しようと思ったのかもしれないが、例によって作者がどこまで考えていたかは謎である。
それまで、ほとんど戦いにギミックを用いなかった宮下あきらが、当時のジャンプの定番であるバトルものをどこまで描けるか、私個人は半信半疑であった。
この頃は、連載が長期化するかどうかもはっきりしなかったのか、仲間の死に対しても非常に深刻なトーンである。
さらに、この頃は私個人としてはまだ「民明書房」なる出版社があると信じており、もしくはなくてもまさか書かれていることのデタラメ度が異常に高いことに気づいていなかった。
・大威震八連制覇
男塾三号生との戦い。しかも、学園に十数年もボスとして君臨している「大豪院邪鬼」を倒させるために、江田島平八が仕組んだ戦いということに、確かなっていた。
冨樫の兄が、数年前に開催されたこの戦いで命を落としている、という伏線もあったが案の定うやむやになった。
しかし、「デタラメ」なのに不思議と感動してしまうところがあるのも確かで、大四凶殺で塾生たちが喉から血が出るまで応援するシーン、八連制覇だったと思うが渡れない橋を渡るために全員がつながって「人間橋」になるシーンなどはうむを言わせぬ感動があったように思う。
「三号生と戦う」ことを塾長が指示する段階で、すでに「絶対封建制」などどこへやら。まあでもそれも、深く考えても仕方ない。
・天兆五輪大武会
個人的には基本設定としてもプロットとしても、シリーズ中いちばんまともで面白いのではないかと思う。
前2回の戦いは、戦う理由が実に判然としなかったが、この「天兆五輪大武会」には江田島の大いなる目標があった。
クライマックスでは、70年代末から80年代前半あたりにマンガの設定としてよく登場した「影の総理」みたいなものを、そのまま80年代後半に踏襲している。さんざん奇想天外な戦いを繰り広げて最終的には「お約束」に落ち着いたわけだが、そのあたりも現状のジャンプ連載作品と比べると驚くほど淡泊である。
たとえば藤堂豪毅と桃との因縁など、もう少し掘り下げられるかと思ったらそれもなかった。しかし、トラウマの描写とその解決をダラダラ続けるのが定番になりつつある現在、この潔さは読んでいて面倒がなくていい。
バトルものとして強調すべきは「トリックの多様」である。
当時、格闘マンガの流行としての「気」も出てくるが、「ドラゴンボール」のように個人の戦闘能力が数値として上がっていくわけではなく、量的な比較が不可能なトリック重視であったことは、「北斗の拳」などと比べても大きな違いであったといっていい。
実はむしろ「ジョジョ」に近いんだよね。
しかも、個々の能力に「キン肉マン」以上に関連性がないため、矛盾だらけだが雑誌で読んでいるぶんにはあまり違和感がない。
「キン肉マン」は基本的にレスラーなので、さすがに個人の必殺技などはきちんと保持していなければならない。だが本作の場合は、戦士が必ずしも「拳法家」であることすら絶対条件ではない。
だからこそ、たとえば「鞭と鳥」を必殺武器にしていた男爵ディーノが次に登場してくるときにはマジシャンになっていても、物語は破綻しないのである。だいたい、連載で読んでいるとよほど熱心なファンでないかぎり、雷電とかディーノがどんな得意技を持っていたかなんて忘れちゃうしね。
そういう意味では技としていちばん整合性のあったのは、ボクサーであり「ニュー・ブロウ」を毎回開発していた、という設定のJかなあ。
最後も、宮下あきらとしてはまずまず整合性がある方で終わったと思う。
バトルものとしては、「技」の面白さから兄弟間の因縁対決の面白さへとシフトさせていった「北斗の拳」や、とにかくリアルタイムでつっこみを入れられてしまう(それが魅力と言えば魅力なんだが)「キン肉マン」よりは、最後まで「技」にこだわった男塾を私は評価したい。
・七牙冥界闘(バトル・オブ・セブン・タスクス)
「塾長が人質にとられ、マフィアの開催する格闘技大会に男塾の塾生たちが出場させられる」という設定は決してつまらなくはなかったと思う。
ただし、なぜか技に「磁石」を多用したものが多くなったりといったタネ切れ感は否めなかった。
「民明書房」的な解説も、それまではウソをウソとして貫こうとしていたがさすがにおおかたの読者にもウソとバレてしまっていたせいか、ギャグがエスカレートして格闘技ものとしての緊迫感を削ぐことにもなってしまった。
重要キャラ候補として出てきた新入生「東郷総司」は、ムニャムニャな感じで終わってしまうし、キャラのバリエーションがなくなったのかあれほど威厳を持っていたファラオが頭身がどんどん低くなってコメディリリーフとなり、選ばれた戦士で一度も活躍しない者も現れる。やはりそこかしこに迷走の後が見られることは確かだ。
途中でブッたぎられるようにして終わってしまうが、まあ微妙なところだろう。
また、そのブッたぎり方にも味があると感じられるのは、やはり作者がこの頃はノっていたのと、編集者のセンスもあったのではないかと思う。
・五魂遷
再び、お話冒頭の「妙な競技をやらされる」展開に戻る。この頃には終了が決定していたのかもしれない。
「風雲羅漢塾」という男塾のライバル校が表れ、「五魂遷」という勝負をやることに。脇役だった秀麻呂や田沢がクローズアップされるのは彼らにとってまさに「男の花道」であった。連載時はずいぶん唐突に終わったという印象があったが、あらためて読むと最初から幕の引き方を考えていたのかもしれない。
巻末には読みきり作品「やばいYATSURA」が載っている。コレがまた「男塾」風にズッこけたいほどいいかげんな作品で、いつ頃書かれたのかは不明だがやっぱり、
>>作者はそれほど深く物事を考えていません。
を再認識する、シリーズ全体の「オチ」になってしまっている。それにしても、よくこれネーム通ったよなあ……。
・最後に。
amazonレビューの別の人で、「男塾」の戦前教育的価値観にマジ怒りしている人がいたけど、少なくとも言えるのは、作者の意図はどうあれ、「受容のされ方」としてはまったくそのように受け取られなかったということだろう。
「男塾」は、作者が本気か冗談か、とにかく独自解釈の戦前教育的なものが入っていることは確かだが、その上にジャンプのスローガンである「友情・努力・勝利」が降りかかっている。
だから、読者への影響を真剣に考えるなら、そこからときほぐしていかなければならないだろう。まああくまでも「真剣に考えるなら」だけど。
(05.0921)
【雑記その2】・やっとamazonで「と学会年鑑Rose」 と学会:著(2005、楽工社)取り扱い
ずっと「在庫切れ」状態が続いていましたが、やっと取り扱いが始まったようです。
ぜひ買ってください[amazon]。
(05.0920)
【雑記】・「鶴岡法斎のエログロ・ハイセンス Vol.3」〜9/18 於:NAKED LOFT
9月18日(日)、NAKED LOFTで行われた、鶴岡さんのマンガに関するトークイベントに、前回に引き続きゲストとして出させていただきました。
そのレポートです。
ただし、ゲスト参加者としての感想ですし、私自身壇上で緊張もしていたので客さんとはまた違った印象かもしれませんし、記憶違いがあったらご指摘ください。
冒頭、鶴岡さんが「自分におけるマンガ評価のスタンスは、ジャングルの奥地に入って珍しいものを見つけてくるというのではなくて、そこら辺に生えている苔などに着目していく研究者のようなもの」と言ったように、持ってきたマンガ群はコンビニや書店で普通に手に入る、それでいて一般的なマンガ評論文脈からはあまり出てこないものが多かった気がします。
勝新太郎の実録モノやパチスロマンガなど。そして徳弘正也「ターヘルアナ富子」、「狂四郎2030」など。
活字本としては、稲川淳二の怪談本がありましたね。
稲川淳二のしゃべりって、東京育ちの人間にとっては実に懐かしい感じなんですよね。恵比寿生まれだということですが、たけしや高田文夫に近いイントネーションなんです。
現在、テレビでは関西系の芸人が多く、また昔の東京弁もなくなりつつあるので、稲川淳二の語りってすごくしっくりくるんですよ。また、シャレっ気があるんですよね。稲川淳二の怪談話も「そこら辺にあるもの」なんだけど、あらためて聞いたり読んだりしてみると考える部分はありますね。
「釣りバカ日誌」や「じゃりん子チエ」の話があったりなどして、実に普通のたたずまいをしているマンガなんだけども、あまりテキストやトークには乗らないものを解説していくところに興味深いものがありました。
また、「萌え」に関して「子供の頃、ピンク・レディーにハマったら萌えには走らず、キャンディーズにハマったら萌えに走るのでは」というたとえが面白かったです。
私としては、飛び道具的なマンガを紹介。ひとつは前回コロコロものが評判がよかったので「3D甲子園プラコン大作」。事前に「愛のないツッコミってイヤだよねえ〜」と話をしていたこともあって、私もTPOでは意地悪モードでツッこむこともあるんですが、今回は素直に「クライマックスでは感動した」と言わせてもらいました。
言葉足らずだったかもしれませんが、本当に私はこの作品を「リアルとは、そしてファンタジーとは何か?」をテーマにした作品だと思っています。それはファーストガンダムがドロップされてジャリ文化に多大なる影響を及ぼした、同作連載時の80年代前半から中盤にこそ問われていた問題だったと思うんです。その辺、うまくしゃべれたかな……。
また、時間もだいぶ遅くなってから奇妙グルメマンガ「チャンプのディナー」も紹介。まあ、これはかなりハイストレンジネスな作品ではあるんですが、夜遅くなってからの気付けにでもなればと。
持ってくる本の役割として、そういう全体の流れに緩急を付ける刺激剤みたいになっていればいいかな、と思いました。
私個人は、トークで反省点がありました。まず緊張していたことと、どの程度話を自分方向に引きつければいいのかわからなかったので言葉足らずの部分があったこと、それと……笑かそうと思ってだいぶ滑りました! すいません! 当然ですが私がネタフリして自分で落として滑ったところはぜんぶ私の責任です。はい。
壇上の印象としては、今回の鶴岡さんはかなりノっていたのでは、と思います。10時過ぎたあたりでトークにドライヴ感が出てきたように感じましたよ。
出させてもらって、実にいろいろ勉強になったイベントでした。
(05.0920)
【テレビ】・「ハロー! モーニング。」(2005、テレビ東京)
9月18日放送分。
公式ページ。
しょっぱなからぜんぜん関係ない話ですが(ぜんぜん関係ない話から始まるときは当然、本編があまり面白くないということなんですが)、
宮藤官九郎の小部屋 第47回 その1のお悩み837の「お答え」で、
>>これは僕の偏見ですが
>>モー娘やあややは何にもしないでイイ気持ちになりたい男
>>つまり弱っている男の味方です。
>>元気な女の子を見てるだけで元気になれるなら
>>勝手に元気になるがいいさ。
と書いてあることなんですが、私はクドカンの業績は認める者ですけど、これは「何かに荷担しないと生きていくことができない」という、クリエイティビティのない人間の本質的な弱さをわかってないか、あるいはあえて無視するという態度であると思う。
もっと簡単に言えば広義の芸術作品に対して「気晴らし」を重要視するかどうかという問題なわけで、まあ「単なる気晴らしでいいじゃねえか」という呪縛と、おそらくは戦ってきている立場の人(=クドカン)にとっては「気晴らし」に特化した作品というのは見ていて苛立ちを覚えるものだとは思うんだよね。
だけど、やっぱり「気晴らし」程度のものって必要なんだよ。
反面、過剰なまでに受容者が「何かに荷担しすぎる」という場合も当然起こり得るわけで、作品がつまらないとか自分の思いどおりにならないからといって、製作者サイドに罵詈雑言を浴びせてみたり、そういうのはそういうのでちょっと問題だよな(念のために書いておくが、これは「ヒビキ」騒動への揶揄ではありません)。
私は一介の鑑賞者、そして鑑賞者であるということはだいたいにおいて金銭を媒介にして作品を享受するしかない立場である、その立場からこのテキストを書いている。
が、そういう立場からするとけっきょくは「バランス感覚の問題」というつまらない着地点にならざるを得ないんだけどもね。
そして、そうならざるを得ないけれどもそういう意味からの「バランス感覚」は重要ですよ。それは知識の量とかは関係なくて、むしろ心の持ちようで、日々の修行の問題ではないかと思ったりもする(だから、私がそうしたバランス感覚を持っているかどうかは、自分ではわからない)。
ところで、そのまま話は飛ぶがかつて山本夏彦が、「どんな音楽が好きかとか、どんなファッションがいいかと思うのはしょせん消費者というか受け手としての『個性』でしかないではないか」というようなことを言っていたんだけども、ここら辺もバランス感覚の問題であって。
最初にそういうことを言っていると知ってから15年くらい考え続けてきたけど、やっぱり「消費者としての個性」っていうのは重要視されざるを得ない部分はあると思いますね。ちょっと言語化できないけどこれは15年間の経験則的に思う。
で、クドカンのモーニング娘。に対する苛立ちと山本夏彦の苛立ちというのはきっと深いところでは共通しているんだけど、私が言いたいのはそれは「気晴らし」ということに対する態度の共通性ではないかと思う。
さて、思い出したので山本夏彦に対してもう少し書くと、山本夏彦のコラムって「わかってる人」についてしか書いてないのが実に明々白々で、そこがあまり好きじゃなかった。
この人って、自分の書いていることを支持してくれる人が1万人いたとしたら、明確にその1万人に対してしか書いていなかったと思う。
いつか読んだこの人のコラムで、「夏目漱石は面白い面白いと言われているが実はそんなに面白くない。正宗白鳥だってリアルタイムでそう書いていた」というのがあって、このコラムは「夏目漱石」が教養の共通基盤である人が読まないと意味がないし、さらに「正宗白鳥まで読んでいる」というのが「カッコいいこと」でなければ意味がない。
これはたとえば「ウルトラマンにおいて実相寺脚本の作品だけがもてはやされるとしたらそれはおかしい」とか「『13日の金曜日』にだってプロット的に見るべきところはある」といったような主張のテキストと、構造的には変わらない。
後者は広義のサブカルチャーを扱っていて、前者は「夏目漱石」というまずまず超歴史的な作品を扱っているという差にすぎないのだけれど、私の苛立ちを表明するとすれば「なんで『夏目漱石』は説明しないでいいの?」というようなことではあった。
ここまで書いてきたけど、自分で実にどうでもいいと思った。ただ説明ナシで進められる問題定義や議論の「含み」の部分は、実はそれがさも重要なことであるかのように見せるテクニックのひとつであるということだけは言えると思う。
でも、もっと他に重要なことがあるんじゃないかとも思うんだな。……と、こういう書き方も一種の「含み」なわけなんだけど。
そんなことよりさあ、高橋愛が天使のかっこうをしていたことの方がよほど重要だろ。
ハロモニ。歌合戦。
まえけんを交えてスタジオでゲーム的に歌を歌う、という企画。
ここで、まえけんはあややをシャッフルユニットまではカバーしていないことが明らかに(というか、先々週もシャッフルの曲に「え?」という顔を一瞬していた)。
コント。高橋愛って、ブスでモテない友達に、ものすごい傷つきそうなアドバイスをしそうだなと思った。「彼氏なんて自然にできるじゃん」とか言って。でも友達は言い返せないんだな。「それはアンタがかわいいからでしょ!」って。
エリック亀井の毎度ありぃ。ゲストとして新曲を出す松浦亜弥。
亀井が新しい写真集を出すそうだけど、道重は出さないのかな? だとしたら道重にとっては大ショックだと思う。
スタジオライブは松浦亜弥「気がつけば あなた」[amazon]。最近しっとり系の歌ばかり歌っている松浦。やりたいこともわかるし、大人のシンガーへの脱皮への努力もわかるけど、はしのえみやまえけんのものまねを見てもわかるように松浦のパブリックイメージというのはいまだに「GOOD BYE 夏男」とかなんだよねえ。
そこのミゾが、一般視聴者の中でぜんぜん埋まってない気がするんだけど。まあ、出す方が地味でいいと思ってるんならいいけど。
前回の放送
(05.0920)
「つれづれなるマンガ感想文2005」もくじに戻る
「つれづれなるマンガ感想文2005」9月前半
「つれづれなるマンガ感想文2005」10月前半
ここがいちばん下です
トップに戻る